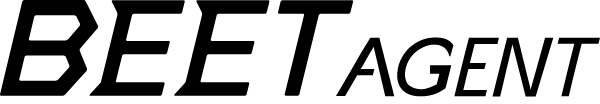《上場企業/リーダー候補》連結決算・開示業務や海外経理に携われる経理@東京都港区の広告系企業

- 企業名
- 株式会社プラップジャパン
- 想定年収
- 650万円〜850万円
- 職種
- 経理
- 勤務地
- 東京都港区

経理業務において、簿記の知識をもっていることで、取引の仕訳や帳簿の作成がスムーズにおこなうことができ、経営状況の把握や財務報告の作成においても自信をもって対応できるようになります。
このように簿記は経理業務に欠かせない知識なので、資格を取得するべきか検討している方も多いことでしょう。
本記事では、経理として働いている人やこれから経理を目指す人材に向けて、簿記資格の必要性や取得するメリット、おすすめの簿記検定や学習のコツについて解説します。簿記以外に有効な資格や磨くべきスキル・能力にも触れます。
|
【経理の転職相談をするなら__BEET-AGENT】 ◆経理特有の転職事情や市場動向に詳しいキャリアアドバイザーが転職活動サポート ◆求人にない企業の内情まで知れるのでミスマッチが少ない転職を実現 |
目次
経理に必要な資格として真っ先に思い浮かべる方が多いのが簿記の資格です。
しかし、そもそも経理業務は簿記資格がないとできないのでしょうか?
ここでは、経理業務における簿記資格の必要性と、どんな場面で簿記知識を発揮できるのかを解説します。
経理業務に従事するにあたって、簿記資格は必須ではありません。
多くの企業では、簿記の資格よりも実務経験や数字に対する基礎理解、PCスキルなどが重視される傾向にあります。
そのため、簿記の資格をもたない未経験者でも、基礎的な知識や意欲があれば経理のキャリアをスタートできます。また、ベテラン経理人材でも、簿記の資格をもたずに活躍しているケースは珍しくありません。
資格は必須でなくても、経理業務において簿記の知識は必要です。
日々の仕訳作業や決算処理、財務諸表の作成などには、簿記の基本的な理解が求められます。
簿記の知識があることで、データ処理や情報の整理がスムーズに進み、正確で信頼できる財務情報をまとめることが可能です。
また、知識がないことでミスに気がつきにくく、ヒューマンエラーが多発することにもつながります。
また、業務の中で「共通言語」として重要な役割を果たします。
主には、以下のような場面で必要です。
簿記は日常的な取引を仕訳という形で記録し、資産・負債・収益などに分類します。
このプロセスは、すべての経理データの基礎となり、財務諸表の作成にも直結します。
決算期にも簿記の知識が不可欠です。
仕訳を通じて蓄積した日常の取引データを集計し、財務諸表を作成します。
簿記の知識があれば各項目の記帳や決算書の数字の整合性が確保され、データの正確性を保てます。
経営判断に役立つ財務分析をおこなう場面でも、簿記の知識が必要です。
財務諸表をもとに売上高や利益率などを分析し、企業の財務状況を可視化します。
簿記を理解していると、これらの分析の前提となる数字の信頼性を確認でき、分析の精度が高まります。
経理業務に従事するうえで簿記資格は必須ではないものの、取得することで仕事の質を高め、キャリアの選択肢を大きく広げる効果が期待できます。
ここでは、経理人材が簿記資格を取得するメリットを5つ解説します。
簿記資格は、採用や人事評価の際に会計知識が備わっていることの証明になりますが、それ以上に実務に役立つのが魅力です。
簿記の基本的な理解を通じて、仕訳や財務諸表の読み取りが可能になるため、即戦力として業務に遂行できます。そのため、経理求人の中には、実務未経験でも簿記2級以上の取得で応募ができる求人があるように、実務実務経験の次に高く評価されやすいです。
簿記を学ぶことで、資産・負債の分類、損益計算、貸借対照表の構成といった経理の基礎的な流れを体系的に理解することが可能です。
資格を取得する過程で実務能力が格段に向上し、複雑な取引や決算業務などにも対応できるようになります。
業務の質を向上させ、正確さとスピードの面で評価されやすくなるでしょう。実務能力が向上すると、結果として残業も減るなど自身にとってもメリットが大きいです。
浮いた時間はさらなる自己研鑽のために使えるため、キャリアアップにもつながります。
簿記資格は経理スキルを客観的に証明できるため、社内での評価が上がる要因となります。
経理部門では、知識や実務経験の証明として評価のひとつの基準とされることが多く、資格をもっていることで昇進や昇格において有利になるケースも少なくありません。
また、企業によっては給与と別に資格手当がつくケースもあります。
簿記資格があることで基礎がしっかりしていることを証明でき、基本的な仕訳や記帳業務以外に決算や財務報告などの業務も担当できるようになります。
実績を積めば、資金繰りや税務調査対応といった幅広い経理業務にも対応可能となり、専門知識を活かせる場面が増えます。
結果的に、キャリアアップにもつながる可能性が高まります。
転職する場合に選択肢が増えることも簿記を取得するメリットです。
まず、簿記を応募条件にしている企業が多いため、応募可能な求人が増えます。
応募条件にはなくても、簿記があるとスキル・知識の客観的証明になるため採用の可能性が高まります。
さらに、簿記資格を取得していることで学習意欲の高さも証明できるでしょう。
経理職を未経験で目指す場合、実務経験の不足がネックとなり、採用側は教育の負担を懸念します。
しかし、簿記資格があることで基礎力があることの証明となり、実務経験の不足を補うことが可能です。
採用の際に評価されやすくなり、転職のハードルが下がります。
とくに経理は人気職種でもあるため、未経験から目指す場合には簿記資格をぜひ取得したいところです。
簿記資格には、「日商簿記検定」「全経簿記能力検定」「全商簿記実務検定」の3種類があります。
初めて簿記の学習をする場合、どの試験を受けるべきか判断に迷うこともあるでしょう。
ここでは、各検定の特徴を挙げ、社会人におすすめの検定を述べます。
日商簿記検定は全国の商工会議所が実施する簿記試験で、社会人にとってはもっともメジャーな試験です。
初級および3級から1級までの段階があり、転職やキャリアアップのために取得したい場合には少なくとも3級以上が必要です。
主に小規模な会社や個人事業主が対象とする基本的な経理知識が身につきます。
実務では、日々の取引を記録する補助的な経理業務や出納管理、領収書の処理といった基礎的な業務に役立ちます。
企業全体の財務状況を把握するための知識を養うレベルで、中小企業の経理や財務部門で即戦力として役立つ知識が得られます。
損益計算書や貸借対照表の作成、原価計算や売上・仕入の管理など決算業務の基礎を習得できます。
とくに2級は多くの企業で経理の応募条件になっていることが多く、取得のしやすさの割に評価も高いためおすすめです。
経営管理や経営分析を行うために求められる、極めて高度な経理・財務知識を習得するレベルです。
特に上場企業や大手企業での決算処理やグループ会社との連結決算、予算管理などを担当する場合に役立ちます。
経営に関わる数値の分析や経営層への報告業務でも貢献できます。
参考:日本商工会議所|簿記
全国経理教育協会が実施する検定で、基礎簿記会計から上級までの5段階があります。
実務に役立つという点では日商簿記検定と同じですが、級ごとの難易度は日商簿記検定のほうが高いと言われています。
全経簿記能力検定1級は日商簿記検定の2級、全経簿記能力検定の上級が日商簿記検定の1級レベルです。
そのため、全経簿記能力検定を取得して中小企業の経理や財務部門への転職でアピールしたいなら、1級があるとよいでしょう。
全国商業高等学校協会が実施する簿記検定です。
受験生の大半は商業高校の生徒なので、社会人になってから受けるケースはほとんどありません。
3級~1級に分かれていますが、こちらも日商簿記検定に比べると難易度が低く設定されています。
最上位の1級は日商簿記検定だと2級相当なので、商業簿記に加えて原価計算ができるレベルです。
簿記資格を取得するべきか迷っている場合、自身の状況に応じて判断してみましょう。
経理としてのキャリアを進むなら簿記の取得に適したタイミングがあります。ここでは、どのようなタイミングで簿記の学習を始めるとよいか、具体的なケースに分けて解説します。
未経験から経理に転職する場合や経理部門への異動を希望する場合、簿記の資格取得は基礎知識を身につけるための効果的な手段です。
とくに簿記2級は仕訳や貸借対照表、損益計算書の基本を理解できるため、面接や異動希望を出す際にも「経理知識がある」とアピールしやすくなります。
経理業務の経験者で簿記の知識がある方でも、基本の簿記知識を学び直すことは有効です。
日々の業務では仕訳や処理に迷いが出る場合や、確認に時間がかかる場合などがあります。
簿記の学習を通じて基礎知識を整理することで、このような場面に役立ち、作業効率が向上します。
知識の再確認や整理はミスの軽減にもつながるため、自信をもって業務に取り組めるようになるはずです。
転職のタイミングで簿記資格を取得することで、転職市場における価値を高めることができます。
客観的な知識を証明できて即戦力として採用されやすくなるため、選択肢も広がります。また、簿記があることで自己成長意欲を示すよいアピールにもなるでしょう。
簿記の取得を目指す方に向けて、学習を効率的に進めるコツを解説します。
簿記は働きながら取得するのが一般的なので、仕事以外の時間をうまく活用することが大切です。なお、自分で勉強するのが難しい人は予備校に通うのも方法ですが、その場合でも自己学習が必要だという点は押さえておきましょう。
最初に、試験日から逆算して学習スケジュールを立てましょう。
無計画で始めると途中で学習が滞りやすく、合格までの道のりが不透明になりがちです。
具体的には、各項目に必要な学習時間を割り出し、週単位で目標を設定することで全体の進捗を管理しやすくなります。
なお、日商簿記2級の一般的な学習時間は独学で250~350時間が目安です。
たとえば、約4ヵ月(16週)での合格を目指してトータル250時間学習する場合、平日2時間、土日に約2.8時間ずつ学習を進めることになります。
この計画だと難しい場合は、学習期間を5ヵ月に延ばす、もしくは平日の学習時間を減らして土日の学習時間を増やすといった調整を加えます。
一通り学習してインプットが進んだら、過去問に取りかかります。
問題で間違えた箇所はそのまま流さずに、原因を徹底的に理解することが大切です。
間違った箇所は、学習内容が曖昧であることを示す貴重な手がかりです。テキストの解説部分に立ち返り、なぜその解答になるのかを確認することで、知識の抜け漏れを防ぐと同時に理解度をさらに深められます。
この積み重ねが、実践力のある簿記スキルの習得へとつながります。
一度学習した内容をそのままにしてしまうと、記憶は徐々に薄れていきます。
そのため、定期的な復習を習慣化することが欠かせません。
1週間に1度は、自分が学んだ内容を振り返る時間を設ける方法があります。特に、前回間違えた箇所や忘れがちなポイントを重点的に見直すと知識がさらに定着します。
経理業務に必要な知識やスキルを身につけるには、簿記以外にも有効な資格があります。
経理に関する資格にはさまざまなものがありますが、特におすすめの資格をピックアップして紹介します。
経理部門で給与計算も担当する場合は、給与計算実務能力検定が役立ちます。
給与計算業務に必要な社会保険や税、労働法令の知識と実務能力を客観的に証明することが可能です。
参考:一般社団法人実務能力開発支援協会|給与計算実務能力検定試験®とは
ビジネス会計検定は、財務諸表の理解力を養う検定試験です。
財務諸表の項目や数値を理解するとともにデータ分析にも役立つため、経理業務に直結します。
簿記の知識がなくても受検可能なので、まずは企業の経営状況を把握する能力を養いたい場合にも有効です。
中小企業における電子会計に対応できる知識とスキルを証明する検定です。
企業経営では、単に簿記で取引を記録するだけでなく、その会計情報を分析・活用し経営に役立てることが求められます。
また、電子申告や帳簿の電子保存に対応できるスキルも必要です。
受検するには簿記の知識と理論が必要なので、日商簿記検定資格を取得した後に取り組むと効率的です。
税理士は、税務の専門家として企業や個人の税務申告や節税対策をサポートできる国家資格です。
税理士資格の取得には、受験資格を満たしたうえで、科目合格制で5科目(会計2科目+税法3科目)に合格する必要があります。
そして、登録するには2年以上の実務経験が必要です。
税理士資格は、経理業務においてとくに税務に関する知識を深め、経営の判断材料として提供できる点で強みがあります。
たとえば、決算や法人税の申告をおこなう際に税法の適用方法を正しく理解し、最適な節税策を提案することや税務調査対応にも役立てられます。
参考:国税庁|税理士試験の概要
公認会計士は、法定監査を実施できる唯一の国家資格です。
取得するには短答式試験(4科目)と論文式試験(5科目)に合格し、3年以上の業務補助などの登録要件を満たす必要があります。
公認会計士資格があることで、財務諸表の作成やチェック、内部統制の評価などに役立ちます。
経理部門では、とくに決算業務や資金調達に関する判断力が求められる場面で有効です。
会計の透明性を確保し、企業の健全な経営を支える役割を担えます。
経理スキルを磨くために簿記の資格取得は有効な手段ですが、もちろん簿記資格さえあればよいわけではありません。
簿記以外にも、経理人材が磨くべきスキル・能力があります。
経理業務では、税制や会計基準に関する知識が不可欠です。
法人税や消費税などの税法や会計基準は、経済状況にあわせて頻繁に改正されるため、決算や税務申告で適切な処理ができるために最新の動向を常に把握しておく必要があります。
また、税務リスクの軽減や節税対策など、自社にとっての価値を提供する経理担当者として活躍するためにも必要です。
経理は単に数字を扱う職種というだけでなく、社内外の多くの人と関わる職種です。
たとえば、経営陣への報告や各部署からの経費申請の確認、監査法人とのやり取りなど説明や調整が必要な場面は数多くあります。
そのため、コミュニケーションスキルが重要です。
これには、相手にわかりやすく伝える力や相手の意図を正確に汲み取るスキルが含まれます。
専門的な内容や規則に関することを経営陣や他部署にわかりやすく説明することで、経理としての信頼性が高まります。
経理業務ではITスキルの習得がますます重要になっています。
会計ソフトやエクセルの活用はもちろん、ERP(統合基幹業務システム)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などのツールを使いこなすことで業務の効率化や正確性が向上します。
また、ITを用いたデータ分析ができるようになることで、経理データから経営に有益な情報を引き出すことが可能です。
ITスキルを身につけることで、経理人材として単に会計データを管理するだけでなく、戦略的な価値を生み出すための基盤を築けます。
複数のタスクや業務を同時に進行したり、効率的に切り替えたりするマルチタスク能力も必要です。
経理業務には、定例的な業務に加えて急な依頼や対応が必要な案件が多くあります。
たとえば、経営陣や他部署から急遽月の予算達成状況や売上報告を求められることや、取引先から請求内容に関する問い合わせを受けることなどが挙げられます。
また、決算期には日常的な経理処理に加え、決算報告書の作成や監査対応など同時に複数のタスクを処理しなければなりません。
このため、優先順位をつけて効率よく業務を進めるマルチタスク能力は経理にとって重要です。
このスキルがあると、タイトなスケジュールの中でもミスを防ぎ、業務を円滑に進めることが可能になります。
経理の仕事は、日々の取引を記録・処理するだけではなく会社の経営に直結する有益な情報を提供することが必要です。
経営視点をもって業務を進めることで、単なるコスト管理に留まらず、収益性の高いビジネス判断や財務面での戦略的提案ができるようになります。
たとえば、データにもとづいたコスト削減案や収益改善の施策を経営陣に提案することで、経営に貢献できる経理担当者として信頼を得ることが可能です。
経理に簿記は必須ではありませんが、実務能力が向上し、人事評価や転職などの場面にも役立つ有効な資格です。
取得する場合は学習に充てられる時間を算出したうえで、計画的に学習に取り組んでみましょう。
CASE
BACK OFFICE CONTENTS
POPULAR CONTENTS
NEW REGISTER
管理部門の転職・求人紹介ならBEET-AGENT